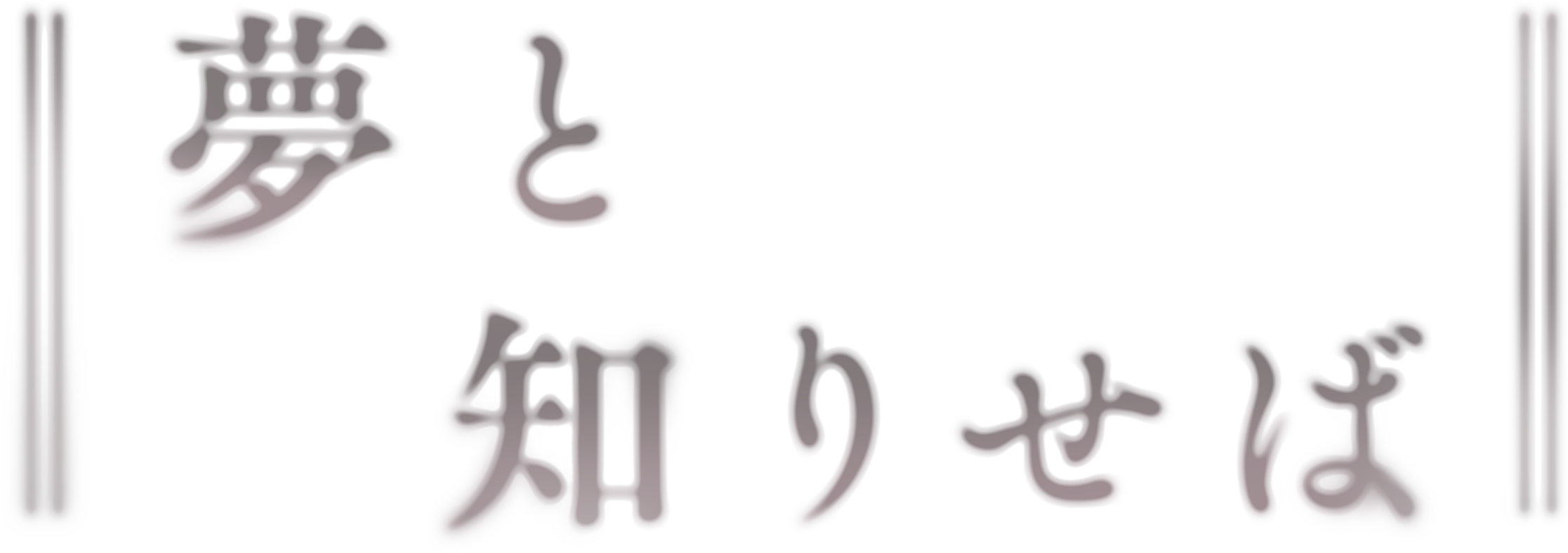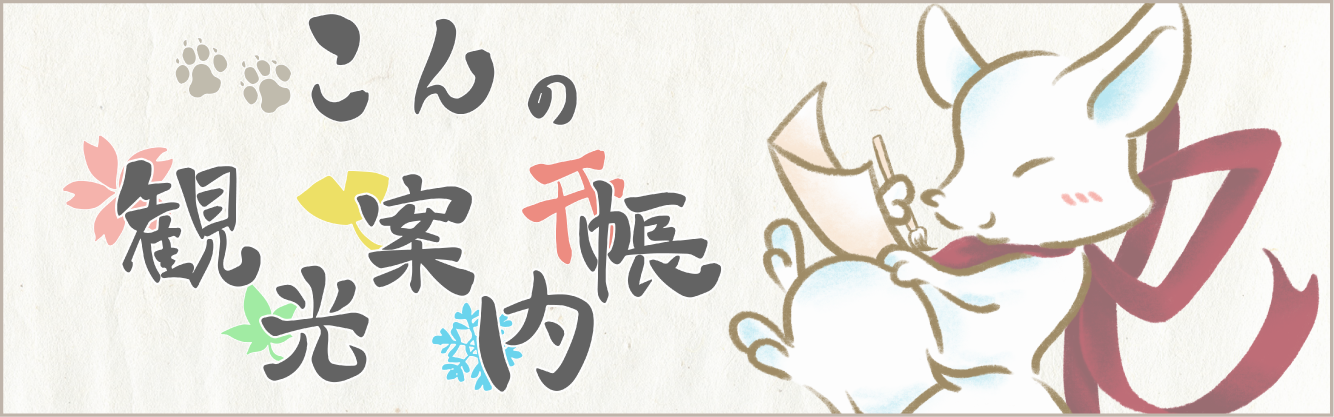1−10 あふみの空も「大文字」
前期の講義が終了すると、苦しい試験期間がやってきた。
講義によって試験方法はさまざまだ。入学して初めての試験ということで、一体どんな形式なのか、どの程度の難易度なのか見当もつかないけれど、そんな学生たちの救世主として、わたしの大学には「試験対策委員会」、通称「シケタイ」と呼ばれる組織が存在する。「シケタイ」に任命された学生は、サークルの先輩などから過去問を入手し、それを学部内で共有するのだ。学生たちはその情報を元に試験に臨むのだけれど、教授たちもそれを分かっているので、いざ受けてみたらまったく見たことのない問題だった、ということも少なくはない。
間崎教授の「日本古典講読基礎論」は、「伊勢物語のおもしろさは何か。自由に記述せよ」という毎年恒例の問題だった。教授の講義は「単位が空から降ってくる」と学生たちに評判である。黙っていればいい男、その上単位までくれるとなれば、教授の人気は計り知れない。
だけど、わたしは知っている。ただ単に採点が面倒なだけだ。
そして待ちに待った8月。
夏休みに突入したわたしは、名古屋にある実家でのんびりと過ごしていた。
久しぶりに食べる母の手料理や、地元の友だちとの会話は、ひとり暮らしをする前よりもずっとあたたかくて心地いい。掃除も洗濯も買い物も自分でしなくていいとは、なんて贅沢なんだろう!
エアコンがきいているすずしい部屋で、テレビを見ながらだらだらとアイスキャンディーを食べる。これこそ夏休みの醍醐味だ。
あれだけ努力して入学した大学なのに、一度帰省してしまったらもう行きたくなくなるなんて、受験生に怒られそうだ。でも、ああ神様。毎日魔法みたいにご飯が出てきて、冷凍庫を開けたらいつでもアイスがあって、今日着た服がきれいに洗濯してある、このパラダイス。試験を頑張ったんだから、少しくらい謳歌してもバチはあたらないでしょう。
こんな平和な生活が、ずぅっと続けばいいのになぁ。
その願いが打ち砕かれるのは、帰省して2週間ほど経ったある日のこと。
普段は無口な携帯電話に、めずらしく間崎教授からメッセージが届いた。
『明日、19時半に吉田神社前』
相変わらず無愛想な内容である。わたしは居間のソファに寝転んで、天井を仰ぎながら返信を打った。
『むりです。わたし、今名古屋にいるので』
携帯電話を机に置いて、中断していた漫画に手を伸ばす。するとすぐに、先ほどとは違う着信音がわたしの邪魔をした。メッセージではなく電話を知らせるメロディーだ。教授から電話だなんて、永観堂に行った時以来のこと。休みの日に突如宇治へと呼び出されたことは、まだ記憶に新しい。
ああ、いやだなぁ。わたしは泣きべそを掻く子供のように顔を歪めた。絶対出たくないけれど、出ない方がきっと数倍大変なことになるだろう。大凶ばかりのおみくじを引くような気分で、おそるおそる通話ボタンを押す。
「はい、もしも……」
『なぜ名古屋にいるんだ?』
声が低いのは、おそらく電話越しだからというわけではない。台所にいた母が好奇心を引っ提げてひょいっと顔をのぞかせてくる。わたしは上半身を起こし、避けるように母に背を向けた。
「なぜって……今、夏休みですもん。帰省しているんです」
『いつ帰ってくる?』
なぜいちいちわたしのスケジュールを伝えなければならないのか。試験だって不真面目な学生に比べたらきちんとできていただろうし、別に会う約束をしていたわけでもない。
「……まぁ、来週くらいに帰ろうかなとは思っていますけど」
訝りながら答えたら、やっぱりというか、案の定というか。ある程度予想はしていたけれど、この教授、とんでもないことを言い出しやがった。
『明日帰ってきなさい』
「はい?」
『明日の夜までに帰ってきなさい』
「明日って……何で?」
『何で、はこっちの台詞だ。五山の送り火をなぜ見ない。君は何のために京都に来たんだ? そのカメラは置物か?』
「確かに興味はありますけど……いやですよ。久々に実家でゆっくりしているんですから。そんなに写真がほしいなら、教授が自分で撮ればいいじゃないですか」
『とにかく、明日は必ず来なさい。来ないと前期の単位はなし』
ぶっきらぼうに吐き捨てて、教授はぶつりと電話を切った。反論を許さないとでも言うかのように、ツーツー、と無機質な電子音だけが、むなしく耳に響いている。
――今、ものすごく理不尽なことを言われた気がする。たぶん、いや、絶対に。
真っ暗になった携帯電話の画面を見ていたら、腹の底からぐつぐつと怒りが煮えたぎってきた。
さすがにこれは、あまりにも強引ではないだろうか。写真を撮ってほしいがために単位を持ち出して、帰省中の学生を京都に呼び出すなんて。大学に訴えたら間違いなく除名処分だ。全学生に言いふらしてやりたい。やつは菩薩なんかじゃない、むしろ天魔だ!
「ねぇ、今の電話、誰から? もしかして、彼氏?」
振り向くと、いつの間にか背後に迫っていた母が、恋の話をする女子高生のような顔をして尋ねてきた。先日パーマをあてたばかりの髪の毛が、好奇心を表すようにくるくると四方に跳ねている。若々しいのは結構なことだけれど、わたしのこの表情を見て、彼氏からだと思える理由が知りたい。
「彼氏なんていないもん」
「あら、そうなの? あんたが電話なんてめずらしいから。で、彼氏は何て?」
「だから、違うって!」
いらだちをぶつけるように叫ぶと、母はなーんだ、と残念そうに唇を尖らせ、台所へと戻っていった。
乱暴な仕草で携帯電話を放り投げ、ぼすん、とソファに体を預けた。放置していた漫画を再び開く。特殊な力を持った主人公がヒロインを救う王道の少年漫画だ。父が昔買ったもので、長らく押し入れにしまわれていたのだけれど、なんとなく引っ張り出して読み始めたらとまらなくなってしまった。現在12巻、残すところあと20巻。これを読み切らずに京都には帰れまい。
絶対に行かない。いや、行ってなるものか!
心の中でそう叫んで、決意に固く杭を打ち込む。漫画の続きも読みたいし、明後日には友だちと買い物に出かける予定もある。永観堂から宇治まで行くのとはわけが違うのよ。いくら五山の送り火があるからって、それだけで帰る理由にはならないだろう。……そう、思っていたのに。
――君の撮った写真だから、見たいんだ。
石清水八幡宮に行ったあと、教授に告げられた言葉を思い出した。あの、講義中以外では絶対に他人を褒めない、性悪で傲慢な教授の、精一杯の褒め言葉を。
「……ああ、もう!」
わたしは思い切り息を吐き、読んでいた漫画を机の上に放り投げた。結局帰り支度をしてしまう自分は、本当に都合がいい。
翌日、約束の時刻。
年に一度の送り火というだけあって、日が沈んだあとでも京の街はどこか賑やかで、道行く人も浮き足立っているように見えた。
大学のキャンパスに自転車を停め、いつもより重たくなったリュックを担いで吉田神社の鳥居へと向かう。軽やかな足取りで歩く人たちの中で、ぽつんと、時がとまったように佇んでいる影が見えた。
顔がはっきり見えなくても、雰囲気だけでそうだと分かる。その人のまわりだけ、一切の音が遮断されたような。風が吹いているのに波紋を立てない水面のような。そんな、誰も寄せつけない独特の雰囲気をまとっているから、いつだって目を奪われてしまう。
できる限り不機嫌な空気を醸し出して近づいていくと、教授は幽霊を見るような表情でわたしを迎えた。
「……なぜそんな顔をするんですか」
「いや……本当に来たのか」
「来いって言ったのは教授でしょう!」
さすがのわたしも学生という立場を忘れて怒鳴り声を上げた。昨日あれほど強い口調で「帰ってこい」と言ったくせに、帰ってきたらきたでそんな意外そうな顔をするなんて。この天魔! 傍若無人!
教授はめずらしく困ったような、バツの悪そうな顔をして頭を掻いた。
「君はともかく、君のご家族には悪いことをしたな」
「わたしはともかくって何ですか。わたしにも悪いことをしていますからね。自覚してください」
小石を投げるように早口でたたみかけると、教授はぐっと言葉に詰まった。最適な言葉を探しているのか、眼鏡の奥にある瞳がゆらゆら揺れる。わたしは担いでいた三脚を下ろし、ほら、と教授に差し出した。
「それは?」
「送り火を撮るなら必須だと父に言われたので、実家から持ってきたんです。重たいので運んでください」
「結局自分も見たいんじゃないか」
余裕を口元に表しながら、三脚を受け取る。そういう表情が、ずるいな、と思う。あたりまえのことをわざわざ口に出すなんて。言い当てられたらわたしは、「うるさいですよ」と子供っぽく顔を背けるしかないのに。
――とっておきの撮影場所があるんだよ。
そう言って教授は、秘密基地に案内する子供のように、どんどん吉田山を登っていく。高揚した街から遠ざかるにつれ、人の気配が徐々に薄まっていった。
どこかで来た覚えがある、と思って、すぐに思い出した。ああ、「茂庵」へと続く道だ。新緑に囲まれひとりで歩いた道。
あれから3ヶ月が過ぎた今、わたしはもうひとりではなくて、目の前に映るのは、あの時一言も言葉を交わさなかった人の背中だ。きらきらと太陽の光を浴びていた木々は今、ささやかな月の光をその身にまとい、気配を消すように黙り込んでいる。
ちょうど「茂庵」のすぐ下あたりだろうか。竹中稲荷社からずっと奥に進んでいくと、片側が石垣になっている細い通路があった。どうやらここが教授おすすめのスポットらしい。周囲に人影はなく、昼間はあれほどうるさかった蝉たちも、ぴたりと口を閉ざしてしまった。息を潜めたら、静けさがそのまま反響して、わたしと教授を包み込んだ。
息づかいすら大きく聞こえるような、そんな夜。
教授に協力してもらいながら三脚の足を伸ばし、望遠レンズをつけてカメラをセットした。最後に使ったのはいつだろう。重たいからあまり持ち運びたくはないのだけれど、今回ばかりはこれがないと話にならない。今後使う機会があれば、そのたびに教授に持ってもらおう。そうだ、そうしよう。
「もうすぐ始まる」
時刻を確認した教授が石垣に腰かけた。夏の夜だというのに空気がひんやりとしているのは、緊張のせいかしら。わたしは高鳴る心臓を抑えながら、じっとその瞬間を待った。
午後8時。
「あっ……!」
遠方に、ぽっとオレンジ色の光が灯った。ちょうど「大」の文字の中心あたりだ。その後あちこちに火がついたかと思うと、みるみるうちに燃え広がって、数分後にははっきりと「大」の文字が浮かび上がった。東山如意ヶ嶽、大文字。五山の送り火が今、始まったのだ。
送り火は、お盆に帰ってきた死者の魂を現世から再びあの世へと送り出す行事である。如意ヶ嶽の大文字については、これが送り火の代表的なものであることから俗説も多いけれど、ふしぎと確実なことは何一つ分からないのだという。いつからか誰かが始め、そして現世まで続いているのだと、背後から教授が教えてくれた。
オレンジ色に燃え上がる炎が、生き物のようにゆらゆらと揺れている。煙が大の字全体を包み込み、夜空高く昇っていく。
ああ、きっとこの輝きこそが、死者の魂そのものなんだ。火種が尽きることをおそれずに轟々と燃え上がるそれは、短くも精一杯生きようとする命のよう。なんて美しく、切ないんだろう。
そのあたたかな光は、鎮火したあともわたしの瞳に焼きついて消えなかった。
「撮れたかい」
炎が消え、再び暗闇に包まれた午後8時半。教授の声で、わたしはふと我に返った。振り向くと、石垣に腰かけていたはずの教授が、すぐ隣に立っている。わたしは送り火の余韻に浸りながら、かろうじてうなずいた。
「はい、えっと、なんというか、うまく言えないんですけど……感動しました。魂が、天に昇っていくようで……」
言いながら、なぜか瞳がじんわりと滲んだ。普段なら「きれい」とか「すごい」という言葉が真っ先に出てくるのだけれど、心が熱くて、この感情をうまく表現できなかった。わたしはぎゅうっと何度も目をつぶったりぱっと開いたりして、涙が頬に伝わるのを堪えた。
別に、悲しいわけではないのだ。でもここで泣いてしまったら、心の中に生まれた感情が「悲しみ」と定義されてしまいそうだから、わたしはどうしても、ここで泣くわけにはいかないのだ。
この意地悪な教授は、こういう時に限って線香花火のようにしとやかな微笑みをたたえ、「ああ」と静かにうなずくのである。長々しい説明もなく、皮肉の一言も言わず。それは、大人の余裕というやつかしら。わたしはたまに、自分がひどくちっぽけでみじめな子供に思えてしかたがない。
教授に三脚を担いでもらいながら吉田山を下りると、忘れていた喧騒が、波のように静かに押し寄せてきた。ああ、先ほどまでいた場所は、確かに現実だったのだなぁ。そう考えたら、安心したと同時に少し残念でもあった。あの浮世離れした感覚は、1年先まで味わえないのだ。
「琴子さん」
大学の正門を過ぎたあたりで、教授が妙にかしこまってわたしを呼んだ。
「今日は本当に、えー……」
「何ですか」
わたしはずびずびと鼻をすすりながら首を傾げた。涙のせいで視界がぼやけて、教授の表情がよく見えない。わたしの視線から逃げるように、教授はふいっとそっぽを向くと、
「わざわざ来てくれて、その、ありがとう」
予想外の言葉に、思わず足がとまった。聞き間違いじゃない。その証拠に、教授の歩調はどんどん速くなっていく。わたしはくすっと笑いながら、教授のあとを追いかけた。
ああ、日が落ちているのがとても惜しい。教授の赤面など、めったに見られるものではないのに!
8月16日、五山の送り火。
それはなんとも愛おしく、少しさみしい、魂を天へと還す約束の儀。
「来年もよろしく」
「えっ」